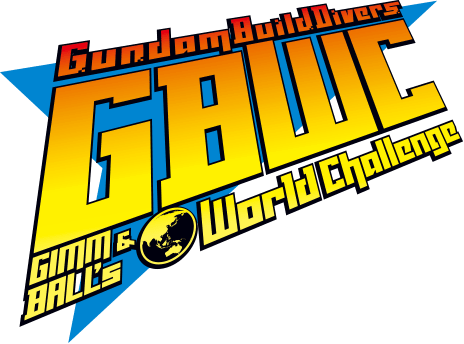「Karrma Chameleon 〜 潜入カメレオン 〜」
「ガンプラ女子校!?」
ボールは、180mmキャノンに換わる、ポリポッドボールの新しいメインウェポンをあれこれ試作していた手を忘れ聞き返した。ジムの自宅の最上階にあるガンプラ・アトリエには、窓めいっぱいからさんさんと陽が差し込んでいる。
「なに聞いてたんだよ、女子校じゃねぇって──」
トイレで洗った手をジェットタオルで乾かす間も惜しみ、びちゃびちゃのまま慌てて戻ってきたジムは、飛沫撒き散らしながら訂正した。
「ガンプラ女学園!」
というものがGBNにはあるらしい、ジムが、トイレットペーパーを補充しようと現れたお手伝いのミス・トレイシーから入手した情報によると。そして彼女は、残念そうにつけ加えた。
「若い頃、そんな女学園があると聞いて知っておりましたら、わたしもガンプラづくりについて大いに学んで、ジムお坊ちゃまと一緒にGBNでガンプラバトルをエンジョイ出来ましたのに」
女学園と銘打ってはいるものの、正体はどうやら、ガンプラづくりがあまり得意ではない女子ファンに、ガンプラの極意を伝えることを目的としたフォースらしいが、いずれにせよきっと、甘い小悪魔の蜜したたり香る、麗しくあやうい愛の巣窟に違いない、間違いない。ジムとボールは夢想した。
それまでの時間、二人は、シモダから貰った未完成の多目的統合コンセプトウェポン・モジュラーパーツ『GHL‐TBA』を、ジムが個人所有している射出成形機でリアルモデリングし、それぞれガンダムストームブリンガーとポリポッドボールのオリジナルウェポンとして完成させるべく試行錯誤していた。
「ったく、あのキュベレイ、なんだったんだよ!」
手も足も出せず、出す暇も与えられず、ただポリポッドボールの180mmキャノンを潰されたボールは、胸くそ悪そうに思い出した。
「つーか」
そんなキュベレイの拡声スピーカーから吐き出された声を、ジムは思い返す。
「アレに乗ってたダイバーって声、女子だったよな」
「けど、なんか凄っげー口悪かったし……ウチの姉妹(きょうだい)より酷かったし、僕からしたらあんなの女子のうち入んないって!」
言われてジムも、ヴィオラのヒステリーを重ねた。確かにそうかもと同意する。
「にしても、GBNにログインしてから、驚くことありまくりじゃね?」
「ホント」ボールはうなずいた。「キュベレイの強襲もそうだったけど、いきなり闇金型マフィアにログアウト出来なくされるわ、かと思ったらゴールデン・ポリキャップのおかげで、GBNから出られるわ」
「だいたい──」と、二人は疑問を重ねた。ゴールデン・ポリキャップっていったいなんなんだ? ヨシとシモダはそいつを謎の輝きに包まれ託されたって言ってたけれど、ならあの二人はどうして託された? 輝きの正体は? それって、自分たちにゴールデン・ポリキャップのことを告げたのと同じ輝きなのか? しかも、レジェンド・ガンプラのビルダーは全部で7人、果たして残りの5人って、いったい。
──なんて、いまは考えている場合じゃない。夢にまでみた男子憧れのパラダイス、ガンダム女学園。桃源郷の中で繰り広げられているであろうキャッキャウフフを、なにがなんでもこの目に焼き付けなければ。
「けど、んな男子禁制の秘密の花園、どうすりゃ……?」
ジムがくじけかけた、その時、
「諦めるなジム!」
彼の肩に、熱くたぎるボールの手が置かれた。
「諦めればすべてはそこで終わる……けれど、諦めさえしなければ、たとえわずかだとしても、可能性という名の道は絶対に途絶えない!」
「ボール!」
「ごきげんようー」
「ごきげんようー」
それはまるで小鳥たちのさえずり。
澄んだ小川の流れのように清く、青空に咲く太陽のように明るく、早春に実った豊かな果実のようにピチピチと爽やかな少女たちが、制服のスカートを花びらのごとくヒラリひるがえしながら、ニッパーを、デザインナイフを、コンパウンドを、エアブラシとコンプレッサーを手に、今日も集う花園の名は『ガンプラ女学園』。その正門玄関にて華やかに戯れていたさえずりが、なにやらふと、お淑やかなささやきに変わった。彼女たちの憧れの視線が一点に集中し──自分に注がれるのを、学園で唯一の男は、学舎内をめざしつつ心地よく感じた。
「学園長ってホントに素敵ね……」
「寡黙でクールなところがたまらない……」
「あの人にだったら、わたしの大切な初めてをあげても、後悔しない……」
まるでそんな声が届いて聞こえそうだった。
彼はダイバー名を『ロック』といった。どんなダイバーにも負けず、一番にガンプラづくりを愛していると自負していた、心の中では。
そんな彼はある日──まだフォースを組む以前、GBNの中で突然眩い輝きに包まれ、謎の声に『女子にガンプラづくりの楽しさを広めて欲しい』と告げられ、黄金に輝くポリキャップを授かったという。
その頃のロックは心の中に住まう男だった。人に声をかける事に尻込みし、かけられれば怯えていた。それでも、気づけば手に握られていたゴールデン・ポリキャップを目の当たりにした瞬間、届いた声に従わねばと心がざわついた。
しかし、どうすれば女子にガンプラづくりの楽しさを広められるというのか。
GBNの道端に立ち説いてみようとした。まるで訪問販売のようにフォースネストを訪ねて回ったりした。しかしどれも上手くいかなかった。
幾多もの挫折を重ねた末、彼は、最後の賭に出た。
口下手ながらもなんとか数名の女子を集うと、彼女たちをメンバーとして──生徒として、自身のフォース=ガンプラ女学園を設立した。ゴールデン・ポリキャップを学びのシンボルに置いて。
はじめは生徒の数もわずかだった。しかし、もっぱら女子にガンプラづくりの楽しさを伝えようとする希有なる学園の噂は、日ごとダイバーの間に伝播し、気づけば、知る人ぞ知るまでに広がっていた。それに伴い、ロックの鮮やかなるガンプラテクニックに注がれる恭敬のまなざしも数を増し、受けた羨望はたんだんと彼の中に自信となって蓄積され、口数は少ないままながら瞳の奥には燃える炎が宿るようになり、次第に己を着飾り見せることにも目覚め、いつしか彼は、女子生徒の視線にさらされる快感の虜になっていた。
そんな彼のもとに、今日もまた、新たなる子羊がやって来る。
ひとつしかない教室、ホームルームの教壇に立ったロックは、居並ぶ女子生徒たちを静かな流し目で見回すと、
「あたらしい仲間を紹介する」
瞬間、教室内が色めきだった。皆がわくわくと顔見合わせる。
ロックは教室の入口を見向いて、
「入りたまえ」
ドアの奥に向けて告げた。
「はい!」
返事の声は二つ重なった。
女子生徒たちが一斉に注目する。
その視線の中、入口のドアが開き、二人は現れた。
「ジム江です」
「ボル美だニャン!」
ビューティー&キュートな容姿に「わっ!」と教室が湧く。
「わたくしたち、ガンプラのこと、右も左も裏も表もさっぱり存じません」
「なので諸先輩おねぇさま方、手取り足取り腰取り胸取り、なにとぞアツーいご指導」
「よろしくお願いいたします!」
最後にもう一度、二つの声が重なった。