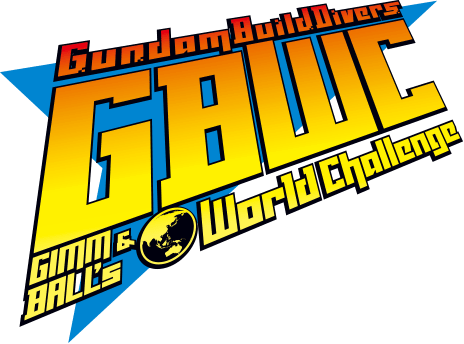「Heart of Glass 〜 割れたこころ 〜」
「あー、マズいな」
「うん、マズいね」
思わず声に出したくなる不味さ、それが三木亭の味、
「──なわけないでしょ」
立ち食いカウンターほどの高さで固定したポリポッドボールのマニピュレータアームをテーブル代わりに、器用な箸使いで蕎麦を口に押し込んでいる(すするのは苦手)ジムとボールに向かって、少女は、うしろでひとつにしている髪を結び直しながら、ぼそりと一瞥を向けた。どうやら彼女は、ジムがオーダーしたジャパニーズ・蕎麦ヌードル・ケータリングショップの関係者だったらしい。
「あのさ……」
ジムは、ボールがザルの上で水分を失い鳥の巣のようにかたまりなっている麺を必死にほどこうとしている隣で、進まない箸を投げ置いた。
見れば、蕎麦を運んできた青年が、傍らに起立駐機しているゼータガンダムの足もとで、うつわがあくのを待っている。
「そうやって待たれると思いっきし食いづらいんだけど」
「ただでさえ食べにくいんだから」
とうとうボールは、蕎麦ちょこの中身をドボドボふりかけ、蕎麦をほぐしながら、
「終わったら呼ぶって」
「衛星軌道上の店まで帰ってまた戻るの、面倒なもんで」
青年はせかすように告げた、なにやらそわそわしている。
「使い捨て容器とかにすりゃいいじゃん」
「本格志向だから、ウチは」
少女がジムに答えた。
「つーか」ジムは、箸で絡まった蕎麦をもてあそびながら「なぜに宇宙に店を出す。そんなの蕎麦ノビて当然じゃん」
「当然じゃないけど」
ふと少女は、青年に目をやった。
「前は、ノビることなんて、なかったけど」
青年は視線を返さない。
なんだかぎこちなく居心地の悪い苦手な空気。「なぜこんな店を選んだ?」ボールが訴えるように睨む、「GBNでケータリングなんてここしかなかったんだってば」ジムが言葉にせず答える。
「残せば、食べないんだったら」
向けられた無表情な声に、二人は思わず揃って少女を見た。
「ただし、代金のフォースポイントはちゃんともらうけど」
「もちろんもちろん!」「注文したら払う、それ資本主義のキホン!」
淀んだ水中からようやくプハッと顔を出したように、ジムとボールは表情を安堵させた。店員の監視の手前、無理矢理にでも完食しなきゃとプレッシャーだったが……もともとこっちはこんなボソボソくそマズヌードルにつきあってるヒマなんてない、DBNからログアウトするために一刻も早くレジェンドガンプラを見つけ出して、ゴールデンポリキャップを手に入れなきゃなんないんだ。そのためだったらフォースポイントなんぞ、なんなら勘定の一〇倍、一〇〇倍、一〇〇〇倍だろうと耳を揃えて──と心の中で言いかけて、二人は「あ!」と思い出した。ゴールデンポリキャップ(偽)すくいの代金に、フォースポイントをすべてつぎこんでしまっていたことを。
少女はダイバー名を『セリカ』といった。青年の方は『ヨシ』。店名の三木亭は、ヨシのリアル世界の名前からとったものらしい。蕎麦の調理とケータリングを彼が、その他の店の切り盛りはすべて彼女が担っている。ゆえにヨシはセリカのことを『コマンダー(司令官)』と呼んだ。ちなみにさきほどジムとボールがいたアミューズメント・ディメンションにも、新規営業開拓に訪れていたそうだ──厨房の洗い場で、セリカからそこまで聞く間に、ジムとボールは6つのどんぶりを割った。セリカは、こめかみに血管を浮きあがらせながら、
「前まではフォースのメンバーもそこそこいたから……ヨシと私の二人だけになった今じゃ、コマンダーどころかリーダー(小隊長)以下よ」
自嘲し言い捨てる。
「二人だけ?」ボールは、汚れたまま山になっている食器を納得の様子で見据え「そりゃ、洗い物も追いつかないよね」
軌道衛星上に浮かぶヨシとセリカのフォースネスト──宇宙ステーションを改装した店は、ケータリング専門らしく、客席はなかった。厨房とガンプラのハンガー(駐機庫)とカタパルト。奥には居住スペースや事務スペースもあるようだが、離れた延し台で蕎麦を打っているヨシ以外、確かに人の気配はない。
「ほかのみんな辞めたの? なんで? ヨシの蕎麦がノビノビでちょー恥ずかしいから? それともヨシがノビノビ男爵だから?」
「だから言ったでしょ」
セリカは、泡だらけのシンクに落としたスポンジを探しながら聞くジムに、カットソーの袖をまくって手を貸し、
「前は、どんなに配達が困難な場所から注文が来たって……どんなに遠くまで届けたって、蕎麦がノビることなんて絶対になかった……けっして、ノビノビ男爵なんかじゃ……」
ふと、蕎麦を打つ音が止んだ。
ヨシの背中が、そっと逃げるように厨房から出ていく。
「あの日までは……」
セリカは彼を見ずに聞こえない声で呟いた。
おいおい、またなんだかおかしな空気が戻ってきたぞと、ジムがボールの方を向くと、同じタイミングでボールも、
「確かに、彼女が言ってるとおりなのかも」
と、ジムの方を向いた。
「……は?」
「あ、うん、あのノビノビ男爵のガンプラ──ヒロって人のゼータガンダム、宇宙から降下してきた時の大気圏突入用ウェイブライダー形態も、ゼータプラスの大気圏内高速機動用ウィングバインダーを装備させたVG可変翼装備の大気圏内高速機動形態も、見事な造り込みだった。しかもそれだけじゃない。フライングアーマーをパージして、ウィングバインダーに空中換装するギミックも、びっくりするくらいスムーズだった。きっと思いっきし気合入れて組み上げたんだと思う、宇宙でも大気圏内でも、どこへでも迅速にケータリングが出来る、究極の……蕎麦の出前専用ガンプラを目指して」
「いやいやいや出前専門って──」
「よくわかったね」
ぼそりとセリカが洩らした。
「そうなの!?」
見ればセリカは、ジムのスポンジを探す手伝いの手を止め、シンクの泡の先に遠い時間を見つめている。
「ヨシの愛機『ゼータキュアノス』……がむしゃらだった頃の、あの人の……出前に懸ける想いの、分身……」
「そ、それよりさ、聞いていい?」この空気はもういたたまれない、ジムは話題を変えようと「オレら、探してる奴がいるんだけど」
ボールも「そうそう、そうだった!」と思い出し、
「君、知らない? レジェンドガンプラって」
「レジェンド……?」
セリカは刹那、思案して、
「……なら、いたじゃない」
「え! マジ!?」
「どこに?」
食いかかると、彼女は皮肉まじりに、
「さっきまでそこに、ケータリングのレジェンド……だった男が」
また蒸し返すか──ガックリとうな垂れたジムの手が思わず寄りかかったのは、洗い終わり積んであったどんぶりだった。慌て支えようとしたボールが足を滑らせる。
割れたどんぶりの数はいっきに二桁に突入した。もはや無傷のどんぶりを数えた方が早かった。
セリカの目がコマンダーの凄みを戻した。
「ジム・タービュレンス、冷やしおろし! ポリポッドボール、たぬきわかめ! 発進します!」
コマンダー・セリカの大目玉の辞令により、どんぶり洗いからケータリング担当に転属となったジムとボールは、払えなかった蕎麦の代金がわりの苦役を一刻も早く終わらせるべく、カタパルトを蹴り、星の海原をめざした──その気配が、ビリビリ震える振動となってステーションのシャフトを伝わりハンガーにいるヨシに届いた。
しかし彼は気にもとめなかった。二人が自分の代わりに行ってくれるならありがたい。その間、『それ』に魅せられていられる──彼は、背後からセリカが見つめていることにも気づかなかった。
ヨシは変わってしまった。以前なら、ケータリングを人にまかせるなんて考えられなかったのに。あの日突然、天から降り注いできたまばゆい輝きに包まれてから……。
セリカは寂しげに深く瞬きすると、ケータリングスーツ用ロッカーの扉にそっとメモをはさみ、ハンガーをあとにした。
*
ケータリングを終え帰路を進むポリポッドボールの行く手に三木亭が見えてくると、ボールは、鰹と昆布の合わせだしの香りが残るコクピットで大きく溜め息をついた。傍らには割れたどんぶり。
「洗って割って、出前で割って……これじゃ、蕎麦代返すどころか、働けば働くほど借金倍増するだけじゃん……」
嘆きつつ、なにかに気づいた、「?」と目をこらす。
三木亭の前で、ジム・タービュレンスが、なにやら帰りづらそうにしている。
ボールは回線を開いて、
「なに? ジムもどんぶり割っちゃった的な?」
「違うし」
無愛想な声が返ってきた。
「じゃ、なんで戻んないの?」
「戻んねぇんじゃねぇの。戻れねーの」
辛味大根の香りが残るジム・タービュレンスのコクピットで、ジムは不機嫌ヅラを満面にしている。
「冷やしおろし蕎麦の出前先でさ、駄目もとで聞いてみたんだよ、レジェンドガンプラのこと、知らねぇかってさ」
「あ、それ、僕も聞いた、無駄だったけど」
この様子なら、ジムも同様だったのだろう、
「いいや、その客、それっぽいの知ってるって──」
ボールは「!」と身を前のめりにした。
「そう言うんだよ、不思議なガンプラがいるって、蕎麦代タダにしてくれたら詳しい居場所、教えてやるって。んなの当然オッケーに決まってるじゃん。で、言われた奴んトコ行ってみたら──」
「いた?」
「いた、ガンプーラが」
ボールは、前のめりにせり出してた頭を大きくガックリとうなだれた。
「……まぁある意味、不思議ではあるかも……」
「不思議っていわないんだよ、ああいうのは、変っていうんだよ。で、急いでその客んとこ戻ったけどもうアウト・オブ・パーリィ……あとの祭り、バックレたあと」
洗い物のどんぶりを二桁割った二人をとがめるセリカの剣幕といえば、それはもう凄まじいものだった。ジムでいえば幼いころ、愛犬ジャニスの毛をワイン色に染めようと、父親が大切にとっておいた一九九〇年ものブルゴーニュをカラにしたときの憤激に、ボールでいえば同じく幼いころ、最年長の姉の勝負ブラを、急流川下りのいかだの旗に拝借したときの憤怒にそれぞれ匹敵した。となると、もし「ケータリングの代金を受け取ってこなかった」なんて聞いたら、それこそ彼女は、もはや激昂で憤死してしまうのではなかろうか。
「…………は?」
ジムとボールは思わず、間抜けな声を揃えた。
エプロン(駐機スペース)へ帰還し、オペラ座の最上階から飛び降りる覚悟で失態をカミングアウトした二人を、しかしセリカは、それまでとは打って変わった穏やかな微笑みで迎えた。
それどころか、
「お願い、私を……さらって……」
大きな瞳のなかで黒目がうっすら潤んでいる。うしろにひとつ結んでいた肩までの髪をほどけば、ふんわり柔らかくウェーブが残って──そっか、セリカって、こんなにかわいかったんだ。
どれだけの時間『それ』に魅せられていただろう。カタパルトの振動が再びハンガーまで伝わって、ヨシはようやく我に返った。次の注文が入ったのだろうか? 誰が蕎麦を調理したのだろう? きっとセリカがうまくやってくれたに違いない、そうだ、彼女にまかせておけば、なんだって──
「そういえば」
ヨシは、セリカの気配がないのに気づくのと同時に、ケータリングスーツ用ロッカーの扉にメモが挟んであるのを見つけた。
そこへ行きたいと言いだしたのはセリカだった。戦場となり廃棄されたコロニー、戦火に焼かれたその都市は、廃墟マニアダイバーたちの間で最近人気急上昇中のディメンションなのだという。
しかしジムとボールは、「どうしてこんなところに?」と聞くのも忘れていた、なぜなら、
「あの店を? 僕らと?」
「そう、あなたたちと私の、三人で」
ついさっきまでポリポッドボールのコクピットを満たしていた合わせだしの香りに代わって、いまは甘く爽やかな柑橘系がボールの鼻をくすぐっている。日ごろ空気のように嗅いでいる姉妹のものとは別物のかぐわしさ、ボールは鼓動が拳で強く胸を打つのを感じつつ、
「三人って……じゃ、ヨシさんは?」
「あの人の名前は、聞きたくない」
「でも──」
一人ジム・タービュレンスのコクピットに搭乗しているジムも、『セリカがどっちのガンプラに同乗するかじゃんけん』に敗北した悔しさを忘れて、
「なんで?」
「理由がなきゃ、一緒にいたいと思っちゃ駄目?」
「いや、その、あの……つーか、オレらまだ、会ったばっかだし」
「女子にこれ以上、言わせる気?」
けれど二人には、やらねばならないことがあった。レジェンドガンプラを見つけ、ゴールデンポリキャップを手に入れて、一刻も早くこのGBNから──
「ログアウト…………なんか、もうしなくていっか!」
ジムは言い放った。
「セリカちゃんみたいなかわいい子と一緒にいられんならもう、ずっとGBNのままでいいんじゃね!?」
「だね!」
ボールも一点の曇りもなしと賛同する。
「よくよく考えてみたら現実世界なんていいことほっとんどないし! 右見ても左見てもドコ見ても人見下したり哀れんだりムカツク奴とかイライラする奴ばっかだし!」
「歩きスマホで横断歩道渡ってたらいつの間にか赤信号になっててクラクション鳴らされたりするしな!」
「家は狭いし母親うるさいし姉妹はいつもパンツ丸出しでありがたみないし!」
「おまけに夏は暑いし!」
「冬は寒いし!」
「現実世界なんて超ビッチじゃね!」
「GBNばんざーい!」
その時だった。ジム・タービュレンスとポリポッドボールの目の前に建っていた三階建てほどの雑居ビルが、遙か上空からのエネルギー指向兵器の一矢を受け、一瞬にして消失した。
遅れて接近警報、ハッと天を見上げる。
陽を背後に鋭いシルエットが向かって来る。この機影、ガンプラじゃない!?
「UAF(無人航空戦闘機)? ……違う、アレって……」ボールは頭のなかのトリセツを検索し「リ・ガズィのBWS(バック・ウェポン・システム)? ……でも、なんかヘン!」
「PBWS(プロトタイプ・バック・ウェポン・システム)!」
叫んだのはセリカだ。
反射的にジム・タービュレンスがライフルを向ける。しかしPBWSは、その照準線を凄まじく複雑なロール機動で翻弄しつつ、ビームスマートガンの威嚇連射を放つと、たちあがった爆炎の中を貫き、次の瞬間、ハイレート・クライム(急上昇)で、あっという間に姿を消した。それはほんの数秒、ジムは瞬きを忘れ、
「つーか早ぇえって!」
「なんだよ! いまの!?」
息を呑むボールの傍らで、セリカが告げる。
「ヨシの、ゼータキュアノスが……来る!」
「!?」
ジムとボールは上空に目をこらした。
機体は姿を見せない。
代わりにガードチャンネル(緊急周波数)が開き、声が届いた。
「セリカを誘拐するつもりで俺たちに近づいてきたなんて……許さない……!」
見れば彼女が、小さな舌をペロリと出している。
ジムとボールは、交信ウィンドウ越しに、驚きの顔を向け合った。