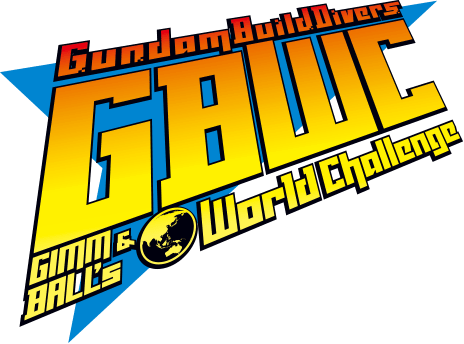「Like a virgin 〜 初めてなの……なぁんてね♪ 〜」
光と闇、裏と表、不浄と清浄、純真に不純、世辞と皮肉、不承不承と唯々諾々、売れっ子にお茶挽き、押し割り麦に挽き割り麦、出稽古と内稽古、ポタージュとコンソメ、富める者と貧しい者、支配する者とされる者、模倣と創造──この世界のすべては二つのモノで出来ている。政治しかり、経済もまた、宗教に宇宙、そしてガンプラ。
それは手が届くほど近くかもしれない。それともあるいは星の裏側か。いずれにせよ聞き及んでいるのは、その場所を知ってしまえば最後、明日は朝日を見られなくなるという、まことしやかな噂だけだ。
一〇名ほどの男たちが集っている。仕立てのよいスーツに身を包み、マホガニーの長テーブルについているのは、下座は三〇代後半から上座に八〇才近く。彼らこそがなにを隠そう、フェイク・ガンプラで全世界を牛耳ろうともくろむ一大闇金型マフィア、そのトップと幹部(カポ・レジーム)の面々だ。
マフィアの集会と聞けば、紫煙満ちる薄暗い隠し部屋を思い浮かべるかもしれないが、しかしそれもひと昔前の話。いまは燦々と陽が差し込む高層ビルの最上階、清浄機が吐き出す空気も爽やかなミーティングルームで、しかし誰もがみな、苦虫を噛んだ表情を浮かべていた。
「件(くだん)の二人組につきましては、現在もその正体を確認中です」
カポの中でもいちばんの若手が、緊張をにじませ報告をあげている。
「しかしGBNの個人情報プロテクトに対する姿勢はかたくなでして……目下、さまざまな方面から圧力をかけ、はき出させようと努力はしているのですが」
「やり方がぬるいのでは?」
隣に座るヤサ男風が、グレースーツの襟元を正しながら、うす笑みの奥に牙をのぞかせる。
「確かにいまのところ、彼らが我々の計画を世に露呈した形跡はうかがえない。しかしそれには理由があると見るべきだ。あるいは、我々が最大の窮地に陥るタイミングを見計らい、脅しを掛けてこようとしているかも」
「ならばこそ、慎重に動かねば」
向かい合う紺色スーツのアンダーボスが、眼光鋭く戒めた。
「軽はずみに行動することのない冷静さを見るに、その者たちは相当の切れ者に違いない。下手に対処し、察知されれば、それこそ取り返しのつかない結果を招きかねんぞ」
どうやらグレースーツはカボの中でもかなりの実力者のようで、アンダーボスの座を虎視眈々と狙っているらしい。他のカポたちが口を出せずにただ傍観するなか、放っておけば話し合いではなく言い争いになりかけたテーブルに、
「それよりも……」
上座よりドンの声が、静かに割り入った。
「気になるのは、GBNの中に閉じ込めておこうとしたその者たちをログアウトさせたという、例のポリキャップのことだ……」
黒のダブルをゆったりと着こなす彼に、全員が視線を向けた。
アンダーボスが頷き、
「確かに我々ファミリーのスーパーウルトラサイバー介入を打ち破るとは、驚愕のツールかと」
グレースーツも同調する。
「しかも詳細は不明、誰がなんのために作ったのかすら……わかっているのはそのポリキャップが、黄金色に輝いていると言うことだけ」
「黄金……ふざけたことを……」
ドンが重々しく目を細めた。アンダーボスとグレースーツが同時に、先に報告をあげていた若手に目で促す。彼は慌てて、
「黄金のポリキャップにつきましては現在、GBN内に協力者を擁立、鋭意調査中です」
「使える者か?」
ドンが問う。
「かなりの手練れかと」
「うむ……」
納得の声を洩らすと、おもむろに立ち上がろうとするドンを、アンダーボスとグレースーツが両側から支えようとした。しかし彼はそれを静かに拒むと、集う皆の顔を大きく見回した。
「いまこそ闇と光とがその役割をただす時、我らが宿願の成就に、御力を添えたまえ……ガンプーラ!」
「ガンプーラ!」
ドンに続き、一同の声がひとつになった。
窓の外には、雲ひとつない青空が広がっている。
夢にまで見るほど待ち焦がれたものが、突然目の前に現れた時、人がそれを事実として受け入れるまでには、焦がれた度合いに比例した時間が掛かるものらしい。
ジムとボールを例としてたとえるなら、いきなり目の前に、まるでアイドルかと見まがうばかりの美少女二人組が現れ、「お二人に一目惚れしてしまいました、もしよろしければ、近くのカフェでお話でもしませんこと」などと声を掛けてきたという事態に直面にしたいま、まずは「なにを高額で買わせようとしているのだろうか?」と疑い、次いで「きっと、綺麗は綺麗だが果たして提示された価格相応の価値があるのかどうなのかよくわからない海をモチーフにした現代絵画にちがいない」と疑いを深め、「まてまて、誘いに乗るとあとから面倒くさい男が現れ脅されるパターンもありえるぞ」と別の疑いをも模索し、あらかたの疑いが出尽くした今も、他にもなにか可能性があるのではないかと、目前の美少女たちを無言で見つめたまま、既に一〇分の時間が過ぎていた。
ジムとボールの尋常ではない警戒心は、二人に声をかけた美少女たち=ノズとマーキーにもひしひしと伝わっていた。これまで暇つぶしに逆ナンした中にも同様に、すぐには誘いに乗ってこない根性なしは少なからずいた。自分たちのあまりの美貌が皮肉にもアダとなってしまっているのかと、そのたびに自嘲してはきたが……まさか、眉間にしわを寄せたまま、無言で一〇分とは。
あるいはこの二人、自分たちの魂胆を見抜いているのか?
もしそうであったとしても、このままではらちがあかない。ノズとマーキーは刹那のアイコンタクトで賭に出ることを確認し合った。
「ごめんなさい、本当のことを言うと、声を掛けたのは、お二人に一目惚れしたからじゃなくて……気になる会話が聞こえたからなの」
ノズは申し訳なさげを装い、告げた。
「…………」
ジムとボールは警戒を解かない。
「ゴールデン・ポリキャップ……って」
二人の目が、小さく見開いた。
マーキーもすかさず加勢する。
「…………きっと、すごく、素敵なポリキャップ、なんだろうなと思って…………」
ジムとボールの眉間がしわを緩める。
ノズは畳み掛けた。
「是非、その黄金のポリキャップを拝見させていただこうと思ったのですが、いきなりそんな不躾なお願いをしても、きっと聞き入れてはいただけないだろうと思って、つい、一目惚れしてしまったなどと偽りを告げて気を引こうと……本当にごめんなさい!」
ノズとマーキーがウルウルと申し訳なさそうに目を潤ませた──次の瞬間、まるで氷の塊が音を立てて溶けるように、ジムとボールは警戒の表情を解いた。
「なぁんだ、だったら最初っから言ってくれればいいじゃん、そんなの全っ然ウェルカムだし!」
俄然アガるジムとともに、ボールも打ってかわったデレ顔を浮かべて、
「こっちこそごめん! 二人のこと疑うみたいな目で見ちゃってさ、ほんとうは嘘なんてつけない、とっても正直で素敵な女の子たちだったのに!」
ノズとマーキーは、賭けが吉とでた事を、視線を交わし祝い合った。
「しかもさぁ!」
ハッとボールに視線を戻す。
「二人のその喋り方、似てるって言われるでしょ?」
「どなたにです?」
聞き返すノズの隣で、マーキーが小首をかしげる。
「『プチ・ルー』の『のぞみん』と『まゆゆん』に!」
ノズとマーキーはハッとなった。まさかGBN内に、ド変化球マイナーを自認する私たちを知っているダイバーがいるなんて。
なんであれ、自分たちがこれまでやってきたアレコレや、これから引き起こすであろうナニソレをかんがみるに、リアル世界での正体を決してバラすわけにはいかない。「どなたですか、その『プチ・ルー』」とおっしゃる方は?」ノズがしらばっくれようとするより一瞬早く、
「誰? それ? ルー? カレー?」
ジムが問うた。
ボールが、噛みつくように言い返す。
「プチ・ルー! ちゃんとした名前は『ル プチ シャペロン ルージュ』って六人組のアイドルバンド! 『のぞみん』はそこのリードギターで、『まゆゆん』はサイドギター! 僕、超大好きなんだプチ・ルー! 曲もビジュアルもよくてさ! そう! このあいだずっと行きたかったライブやっと行けて、しかもチケット最前列でさ! それも真ん前がいち推しののぞみん! 後半ステージ超盛り上がって、のぞみんの汗とか唾とかビショビショ飛んで来て顔とかに掛かってさ、僕あれから今日まで顔洗ってないんだ!」
ノズとマーキーは、心の中で指折り数えぞっとした。もっとも最近のライブでも、一週間は前になる。
「ぞ、存じ上げませんわ……そのような方々……」
思わず表情がひきつる。
「ええ〜! 二人とも雰囲気ものすっご似てんのに!」
「やめれって!」ジムはボールをたしなめた。
「二人ともガチ引いてんじゃん。キモいよね、アイドル・オタなんてさ。オレにはさっぱりわかんね。だってんなの、いっくら可愛くてお気に入りだからって、どんだけ追っかけまわしたところで、別に付き合えるわけでもねぇし、そんなの金をどぶに捨ててんのとおんなじじゃん」
そう言うジムを、ボールは逆に哀れみと蔑みの混じった目で見下す。
「まぁ、このワビサビは、到達した者じゃなければわからないだろうね」
堂に入ったものだ。
一方でマーキーは、癇に障った様子で思わずギッとこぶしを握っている。その手をノズは、そっと抑えると、
「それでは是非今度、黄金のポリキャップを見せていただけますか? 遊園地でガンプラ・デートなんてしながら」
「よろこんで!」
嬉々と返すジムとボールにうふふと微笑むノズの隣で、マーキーも必死に笑みを作る。日取りを決め、別れ去り際、
「そうそう──」
ノズは足を止め、ジムとボールの方を振り返った。
「さっき、ひとめ惚れは嘘だって言いましたけど……なんだか、嘘じゃなくなりそう……」
薄く頬を染めるノズに、ジムとボールは思わず心を鷲掴みにされ、そしてマーキーは、その周到さに感心の笑みを浮かべた。